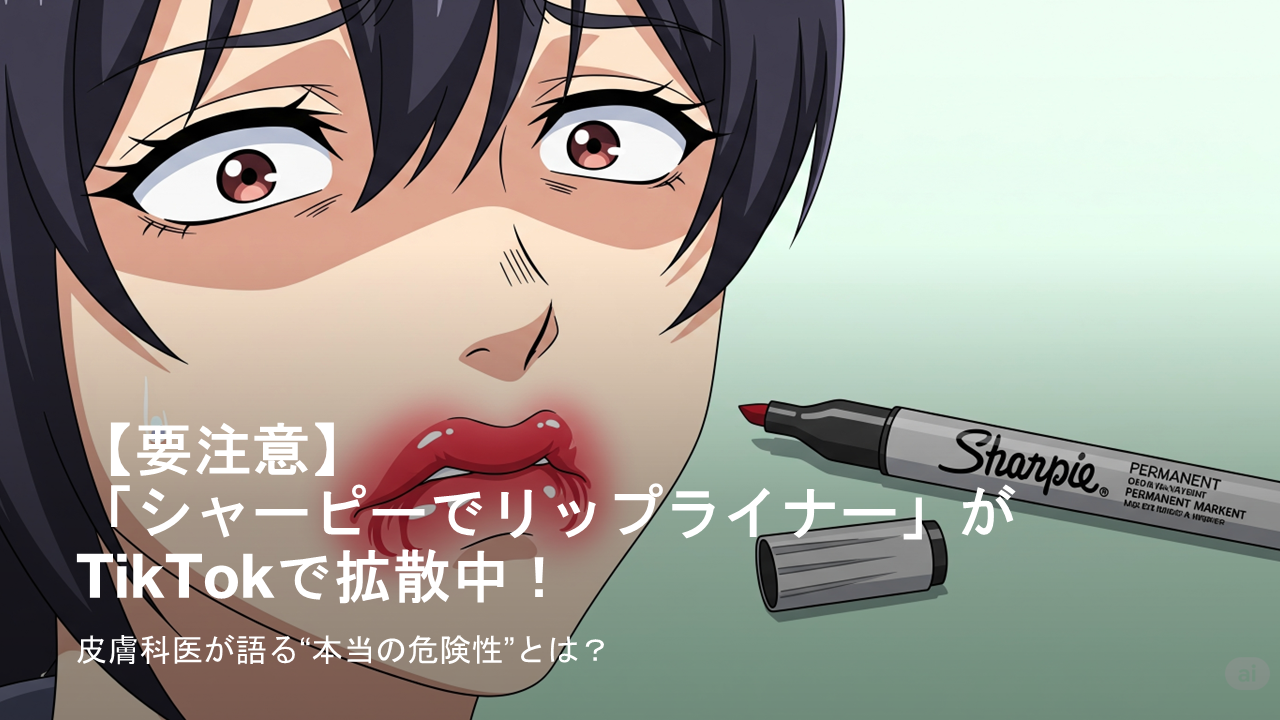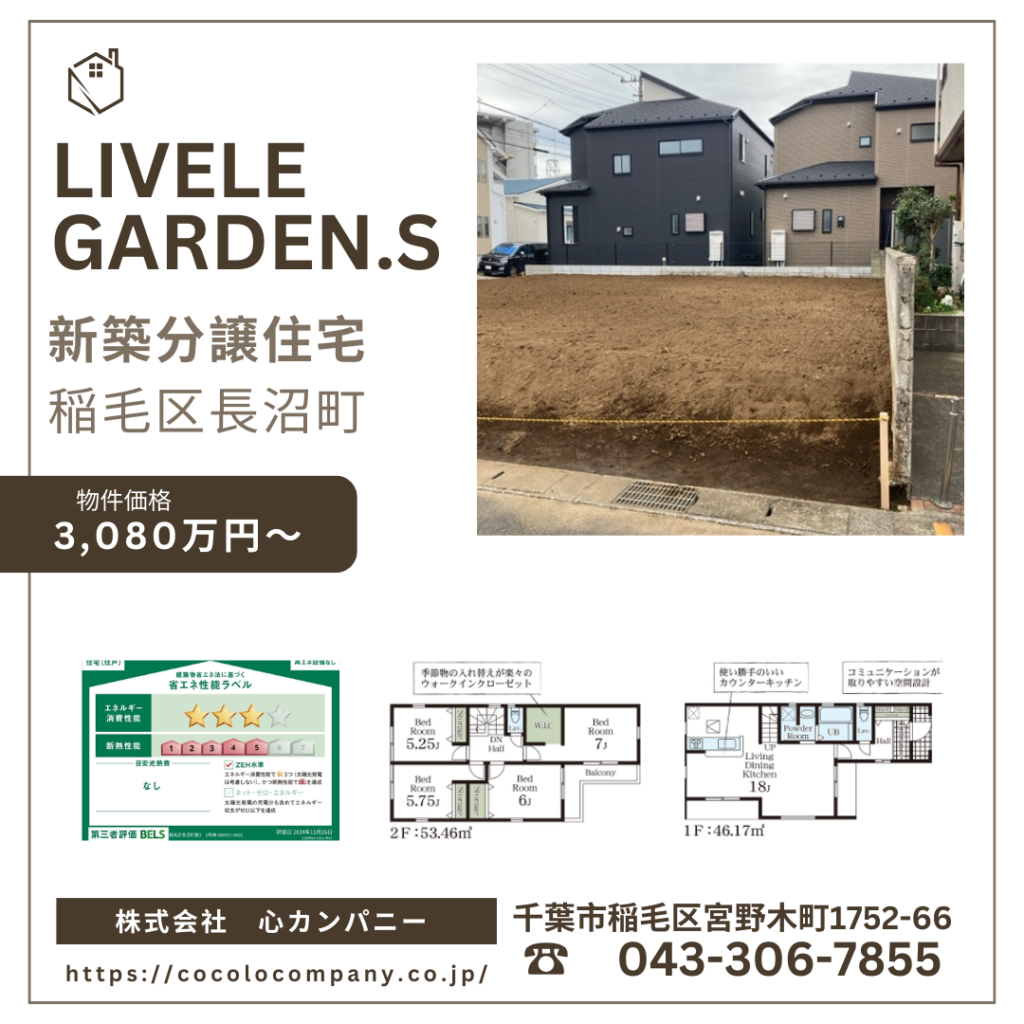日本の「国民皆保険制度」は誇るべき制度ですが、現在、その維持が危機に瀕しています。
その一因が、外国人による国民健康保険(国保)の未納問題です。
特に東京都新宿区では、「11億円の税金」が未納分の穴埋めに充てられており、全国の自治体でも同様の事態が常態化しつつあります。
これは、今や看過できない深刻な問題です。
【背景】
外国人と医療制度の関係とは?

日本では、3カ月以上在留する外国人も原則として国民健康保険に加入することになっています。これは医療サービスを公平に提供するための制度ですが、実際には「保険料の未納」が深刻な問題となっています。
安倍政権時代に外国人労働者や実習生の受け入れが進み、在留外国人は年々増加しています。
それに伴い、医療機関では外国人患者への対応も増加。しかし、保険料未納のまま医療を受け、支払いを行わないケースが目立つようになってきました。
【注目データ】
新宿区で「11億円の税金」が補填に使われている現実

2023年度の新宿区のデータによると、外国人が世帯主である場合、国民健康保険の賦課額は約20億円。
しかし、実際に納付されたのはわずか8億7000万円であり、未納額は11億3000万円にのぼります。
これはつまり、新宿区の一般財源、すなわち私たちの「11億円の税金」が、未納保険料の穴埋めに使われたことを意味します。
しかもこれは、比較的税収が多く、職員の対応力もある大都市・新宿区での話です。全国の自治体では、もっと厳しい状況にある地域も少なくありません。
【板橋区の例】
国別の未納率は驚くほど高い

同じ東京都の板橋区では、国別に以下のような高い未納率が報告されています。
- ウズベキスタン人:86.5%
- スリランカ人:79.2%
- ネパール人:70.8%
- 中国人:34.3%
(ただし世帯数が多く、未納総額は1億1700万円)
これらの未納分は、保険証を使って医療機関で受診した後に請求される診療報酬の原資が足りなくなる原因となり、最終的に自治体が補填する形になります。つまり、ここでも税金が使われているのです。
【全国推計】
未納による国保損失は年間4000億円規模?

板橋区の調査結果を全国に当てはめて推計すると、年間4000億円以上の国保保険料が外国人によって未納されている可能性があります。
これは地方自治体にとって深刻な財政負担であり、地域経済や福祉サービスの圧迫につながります。
とくに中小規模の自治体では、数人の職員で千人以上の外国人の納付管理をしなければならないという現実があり、実質的に未納を把握することすら困難な状況です。
【厚労省の見解と現場とのギャップ】

厚生労働省は、外国人による高額医療費の支出は全体の1.15%であり、問題は限定的だと説明しています。
しかし、医療現場や自治体の実感はそれとは異なります。
「実際には数字以上の負担感がある」「未納や踏み倒しは、制度を維持するうえでの大きな障害」という声が医療関係者からも多く聞かれています。
【解決策はあるのか?】
専門家・自治体の提言

現在、一部の自治体では以下のような取り組みが進められています:
- 滞納対策課の新設(例:新宿区)
- 出入国在留管理局との情報連携(例:横浜市、豊島区)
- 国保未納と在留資格の紐づけ
- 入国時の民間保険加入義務化
- 医療費の前払い制度の導入
しかし、これらは部分的な対応にすぎず、全国規模での制度改革が必要です。
【まとめ】
今後どうすべきか?私たちが考えるべきこと
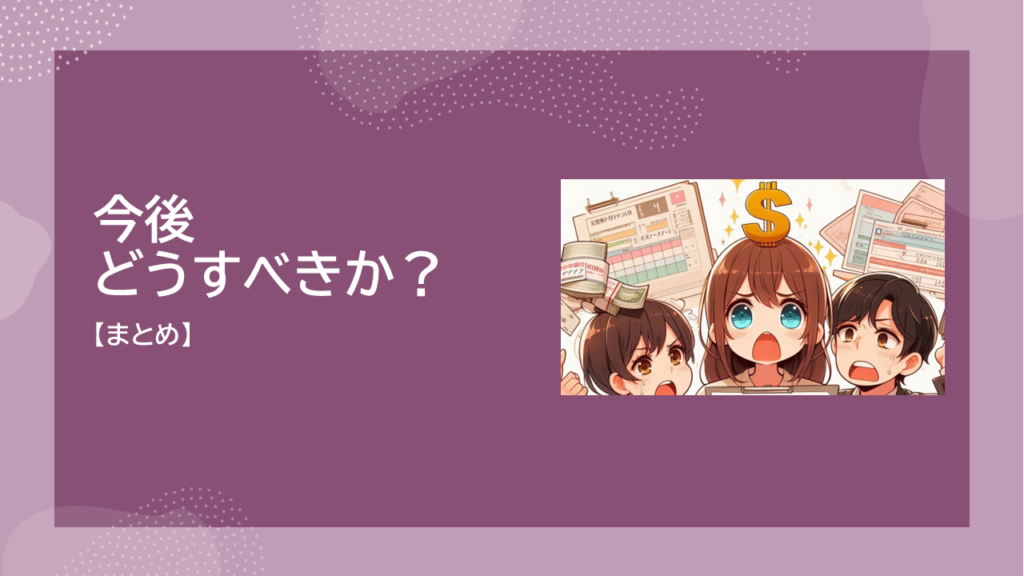
この記事で述べたように、「11億円の税金」が国民健康保険の未納によって使われるという現実は、もはや一部自治体の問題ではありません。全国で起きている医療制度の“歪み”を正すには、以下の視点が重要です。
- 外国人の受け入れ拡大とともに、社会保障制度の整備もセットで行う
- 国保の制度自体を、国際化に対応した仕組みに再設計する
- 地方自治体任せにせず、国レベルでの制度改革を進める
日本がこれからも「公平で安心できる医療制度」を守り続けるためには、誰が医療費を支払うのか、制度を支える税金の使われ方について、私たち一人ひとりが関心を持つ必要があります。
11億円の税金は、決して他人事ではありません。
医療の質を守るため、地域の財政を健全に保つために、今、制度の見直しが求められています。