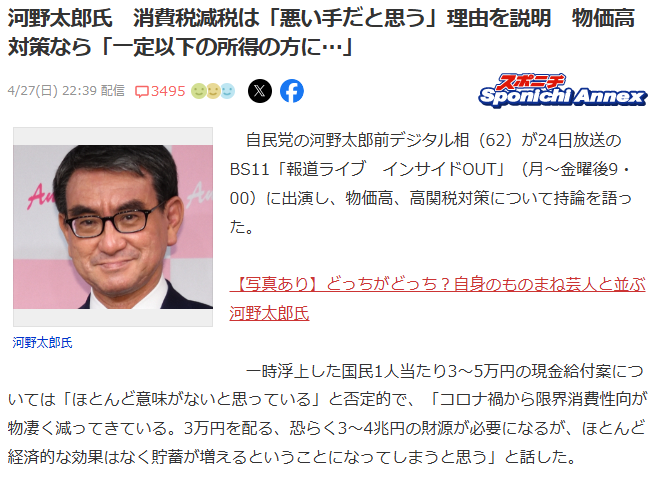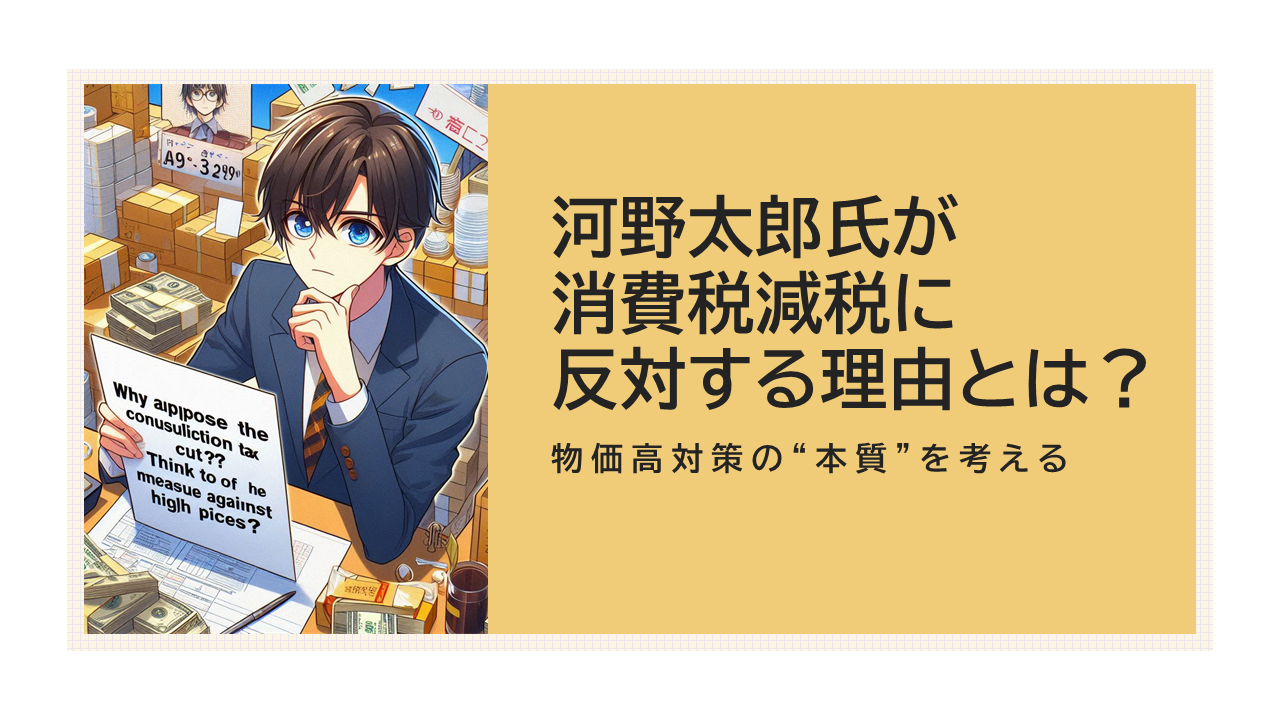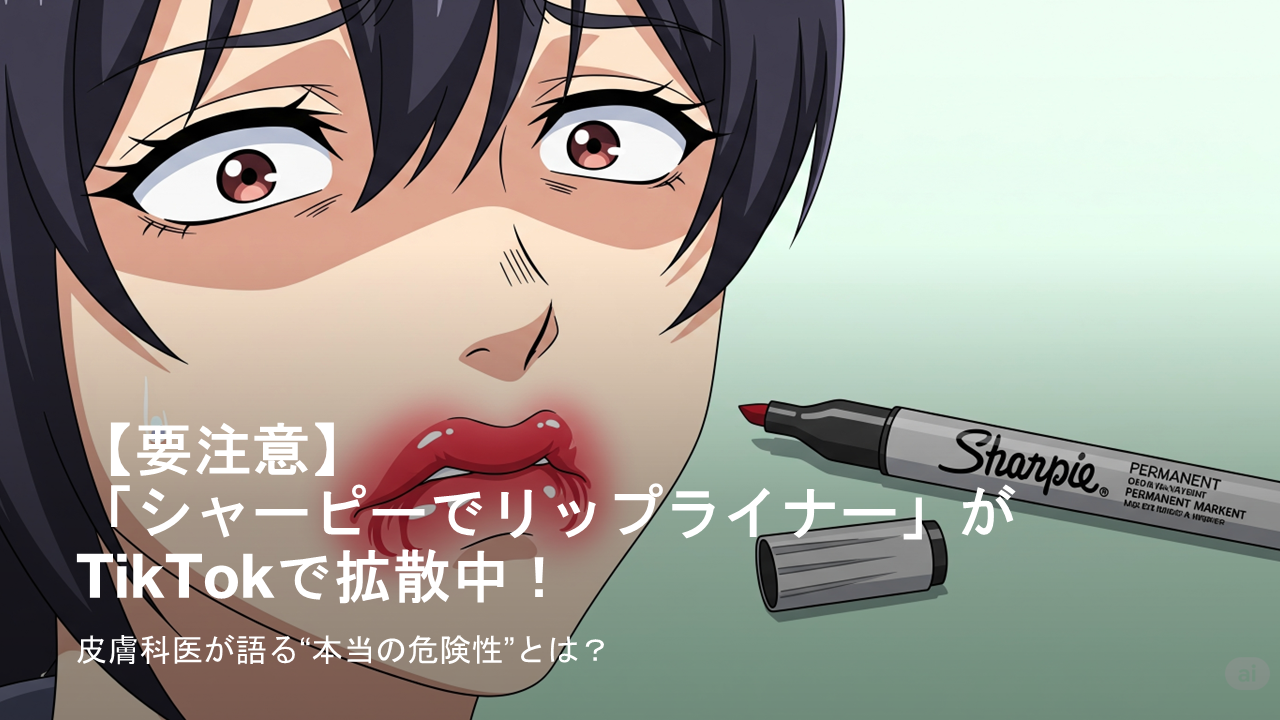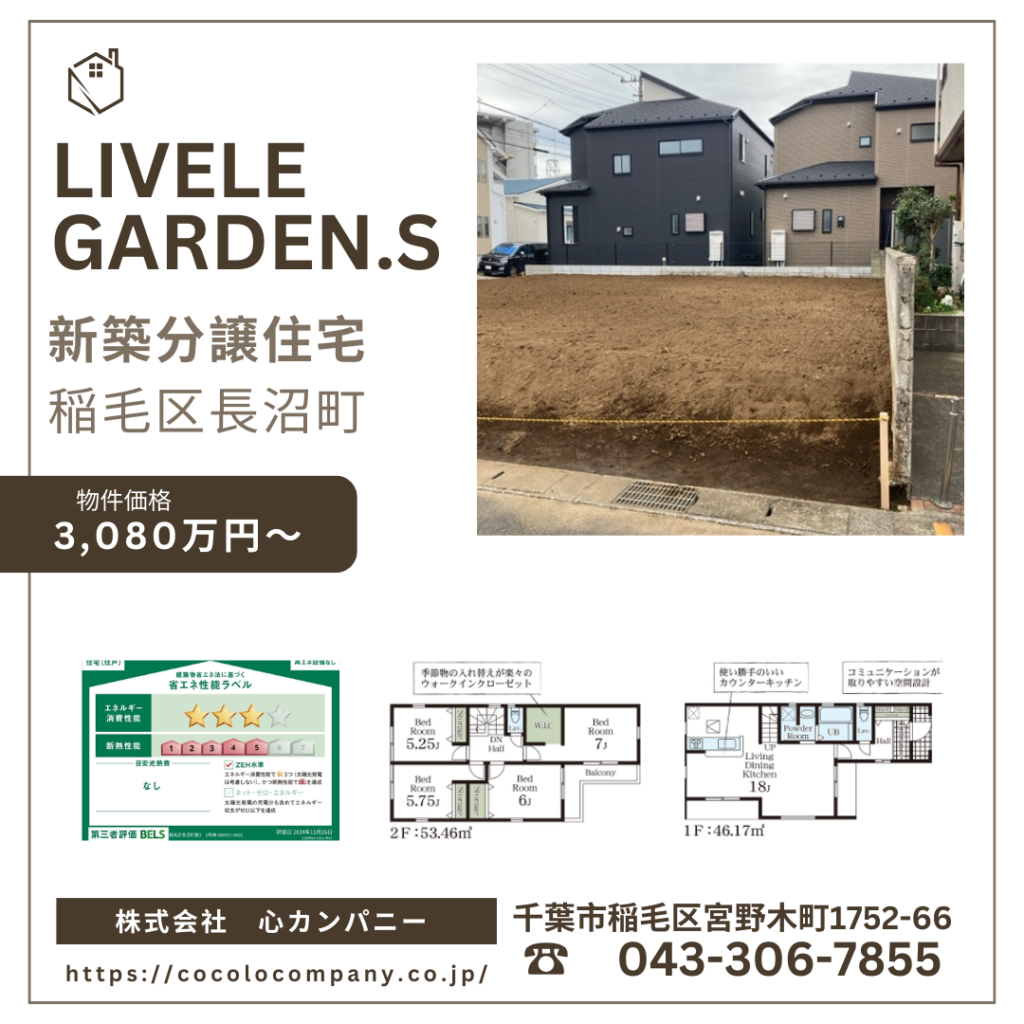消費税減税は公平な対策ではなく、経済活性化にも限界がある
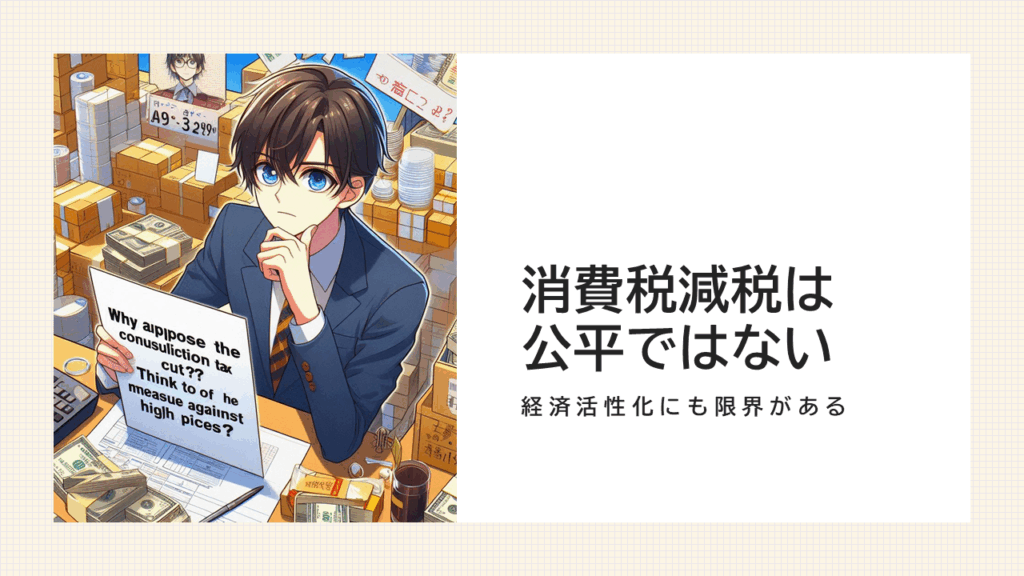
現在、物価高騰への対応策として「消費税減税」や「所得制限付き給付」が議論されています。
この中で、自民党の河野太郎前デジタル相は、消費税減税は悪手だと明確に反対意見を表明しました。
その理由は、「たくさん消費をする高所得者が一番得をする」ためであり、本当に支援が必要な層に届かないという課題を指摘しています。
消費税減税は高所得者に有利、効果が薄い可能性も
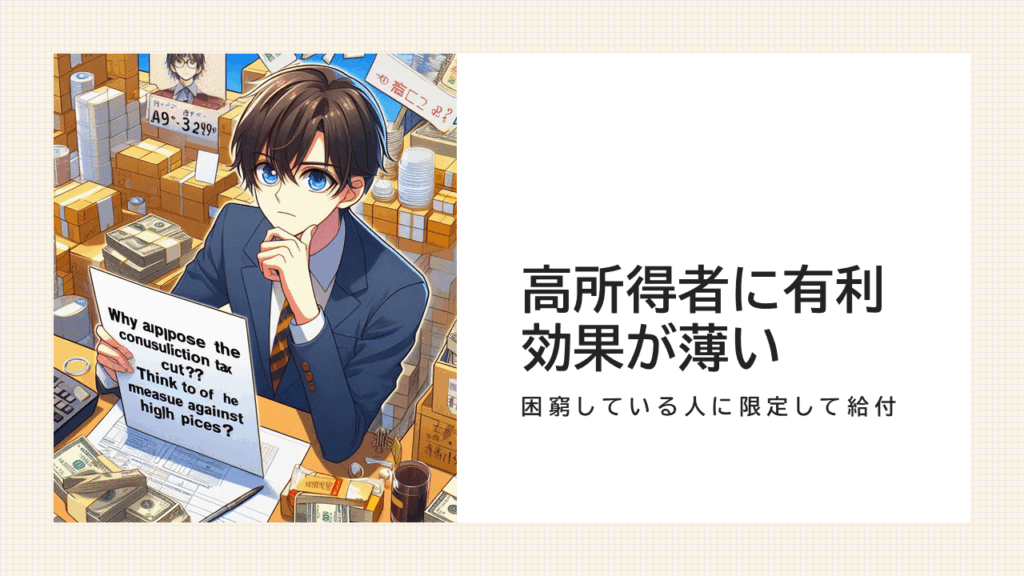
河野氏は、24日放送の「報道ライブ インサイドOUT」に出演し、次のように語りました。
- 「消費税減税は、一番消費する高所得者に多く恩恵がいく」
- 「一定以下の所得層にピンポイントで給付したほうが、消費性向が高く効果的」
- 「現金給付も、限界消費性向が落ちており、貯蓄に回ってしまう恐れがある」
さらに河野氏は、所得だけでなく資産状況もマイナンバーで把握し、本当に困窮している人に限定して給付すべきだと提案しました。
世論の反応は?
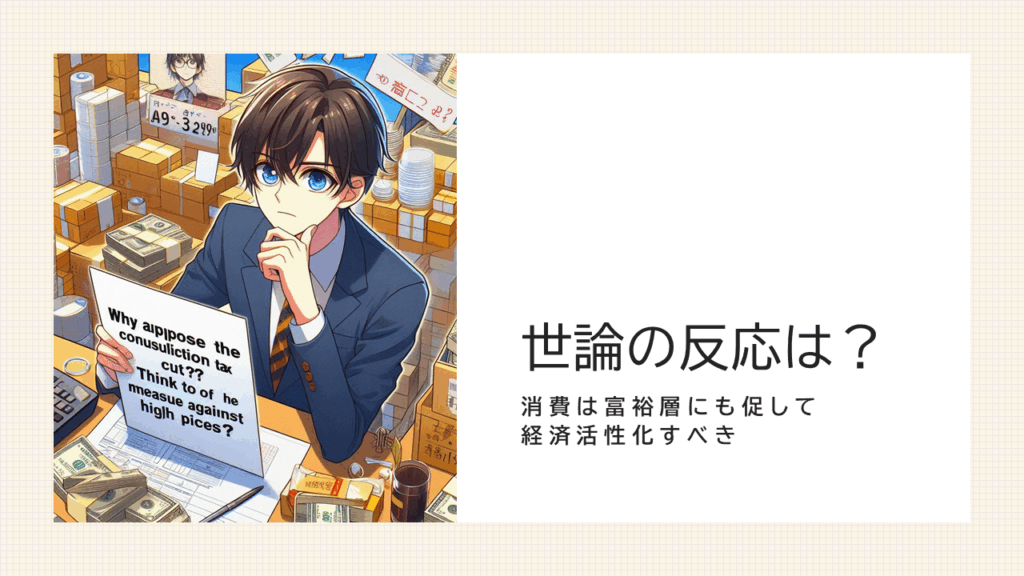
消費税減税に反対する河野氏の発言には、多くのコメントが寄せられました。
✅ 消費税減税賛成派の意見
- 「消費は富裕層にも促して経済活性化すべき」
- 「所得に関係なく、生活必需品の負担軽減は国民全体に恩恵がある」
- 「食料品など限定で消費税ゼロにすれば公平性が保たれる」
❗ 所得制限付き給付に対する懸念
- 「マイナンバーによる資産把握は現実的に難しい」
- 「非課税世帯でも資産を持つ高齢者は多く、制度が不公平になる」
- 「給付対象選別コストや不公平感で結局一律給付と効果が変わらないのでは?」
👀 中所得層からの不満も
- 「高所得者も中所得者も、税金をたくさん払って社会を支えている」
- 「支援は低所得者ばかりで、中間層が置き去りにされている」
消費税減税とピンポイント給付、どちらにも課題あり
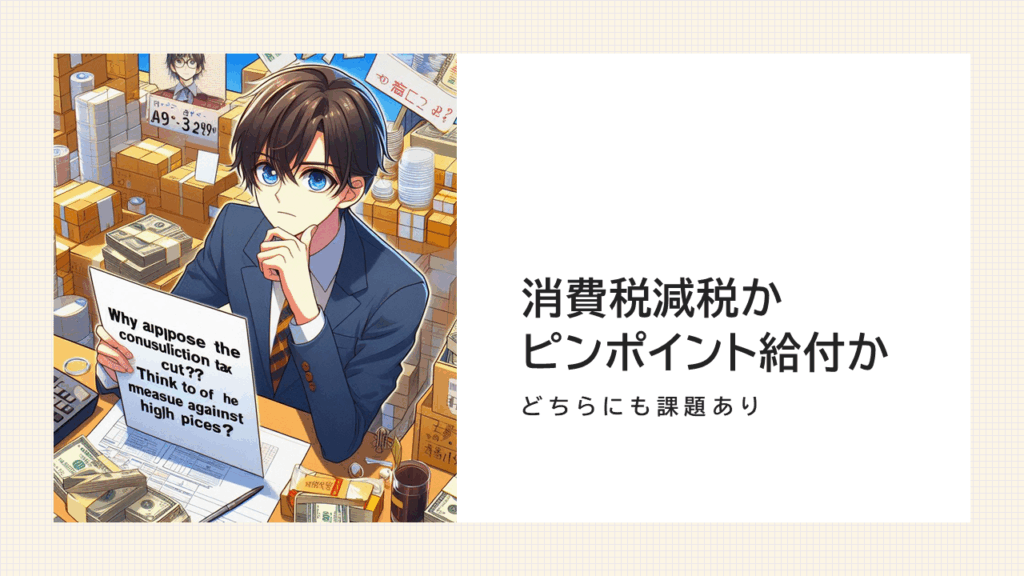
消費税減税は、確かに経済活性化を促す可能性を秘めています。
しかし、河野太郎氏が指摘するように「恩恵の偏り」や「本当に困っている層への支援不足」といった問題も無視できません。
一方、所得制限付き給付にも「資産把握の難しさ」や「選別コスト」の問題があり、決して万能策とは言えないのが現状です。
今後の政策には、
✔ 国民全体の負担感を減らす
✔ 真に困窮する層を的確に支援する
✔ 中間層への配慮を忘れない
といったバランス感覚が求められています。
最後に
私は、以前から気になっていましたが、なぜ、困窮者ばかりに限定しているのだろうか?と疑問に思い、ふと考えたことがありましたので、別の記事で考察します。
関連キーワード
消費税減税・所得制限付き給付・経済活性化・物価高対策・富裕層優遇・中間層支援・マイナンバー資産把握
関連記事
参考記事