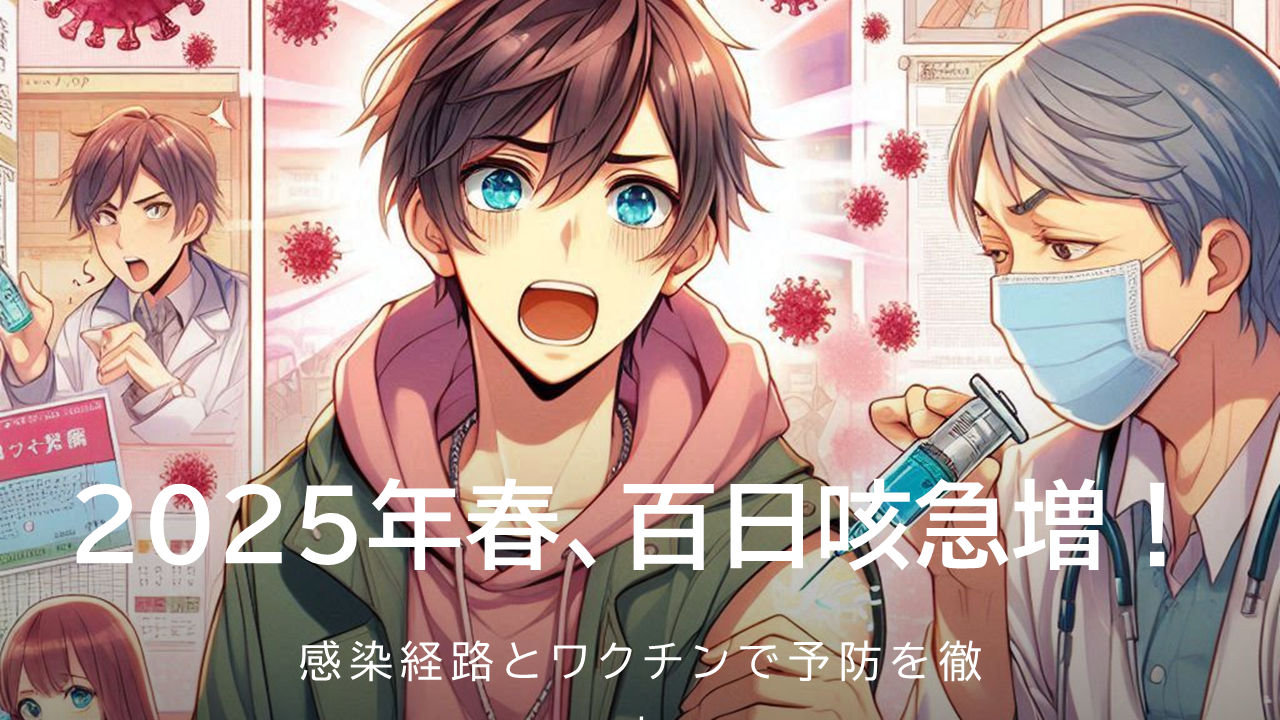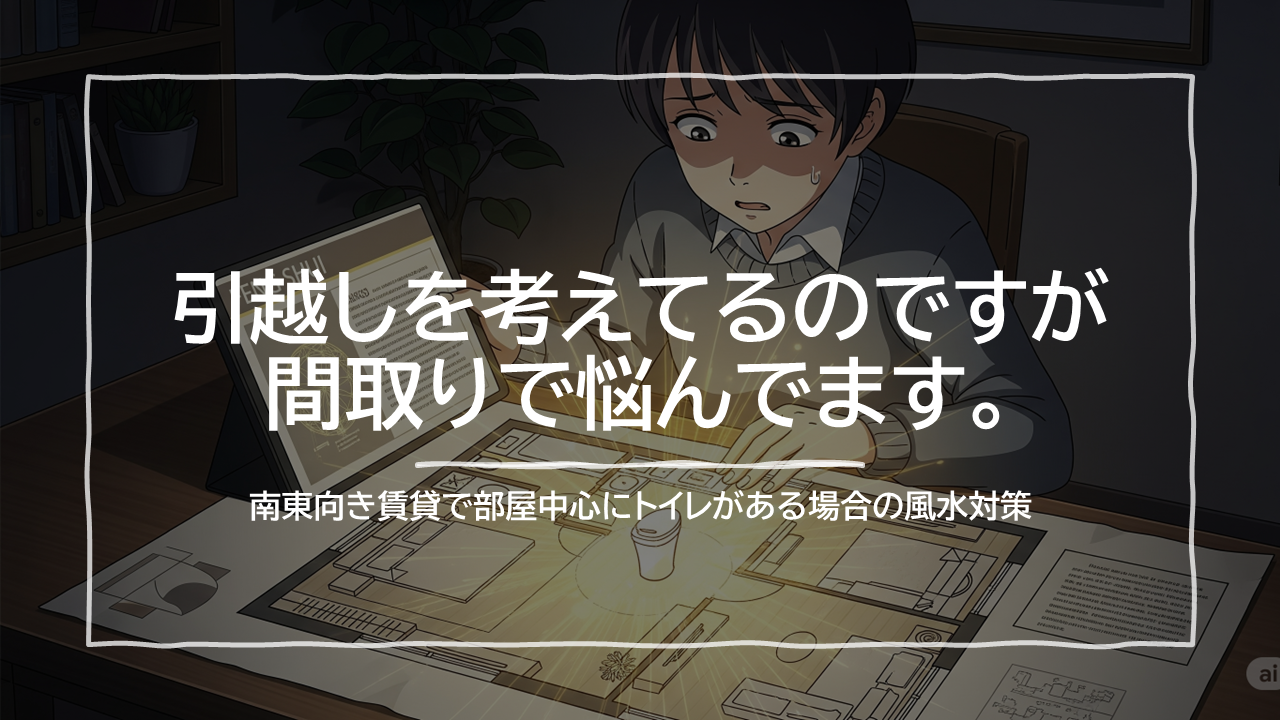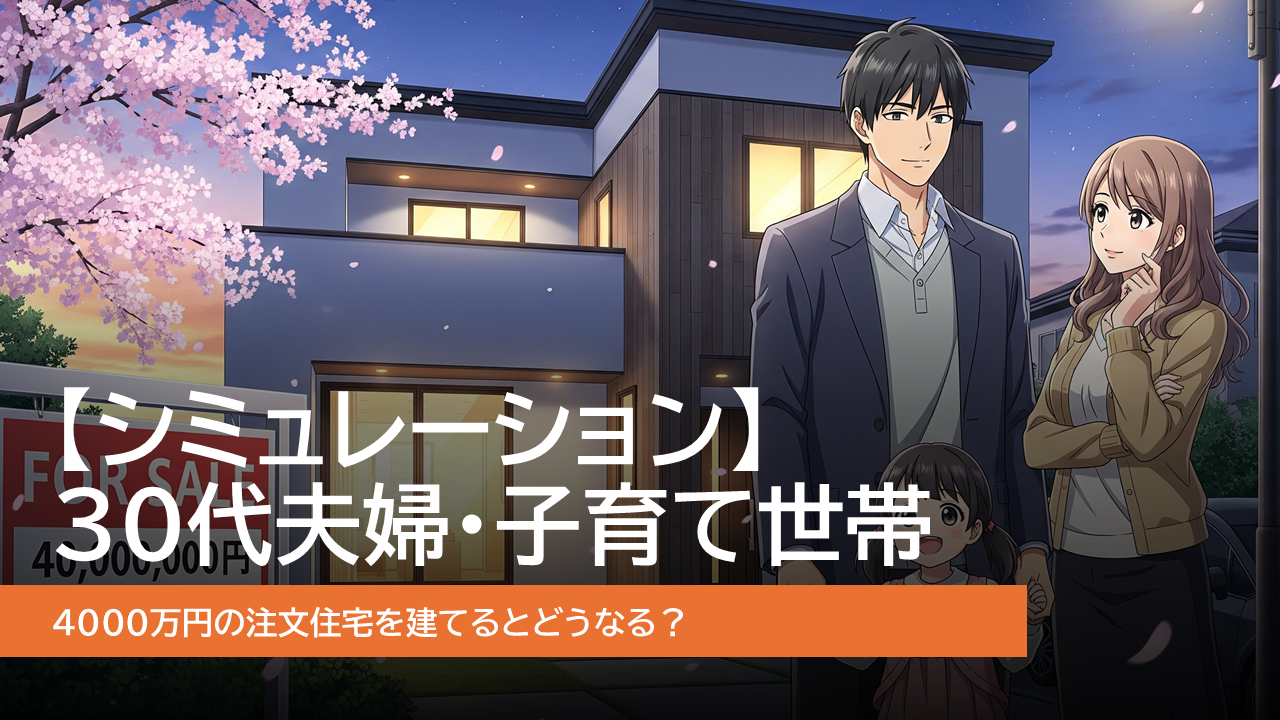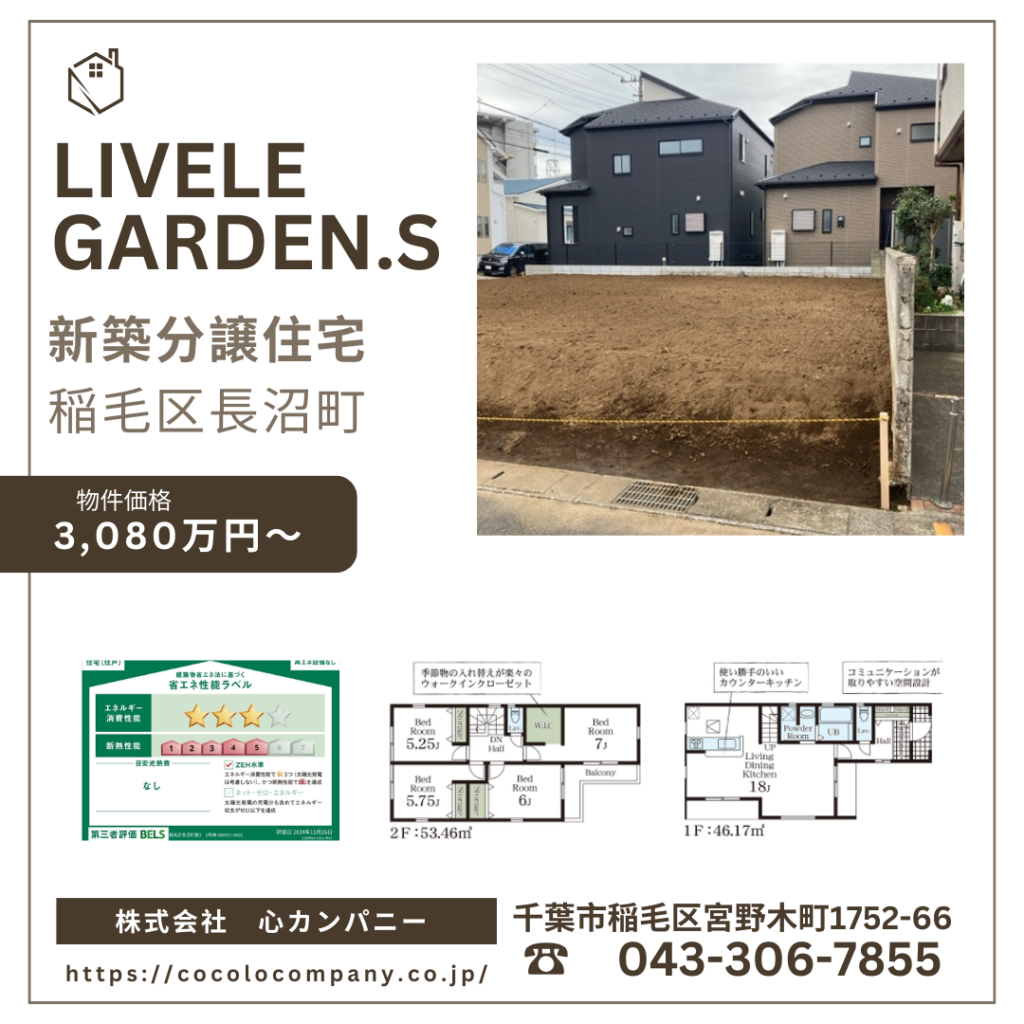最近、「百日せき(ひゃくにちぜき)」の流行がニュースでも取り上げられるようになってきました。
国立健康危機管理研究機構の発表によると、2025年3月末時点での患者数はすでに4,771人に達し、前年2024年の年間患者数(4,054人)を超えています。
特に乳幼児にとって重症化リスクが高いため、親御さんを中心に不安の声も広がっています。
この記事では、百日せきの基本情報、感染予防のポイント、そしてワクチン接種に関する考え方をわかりやすくまとめました。
百日せきとは?
主な症状と感染経路
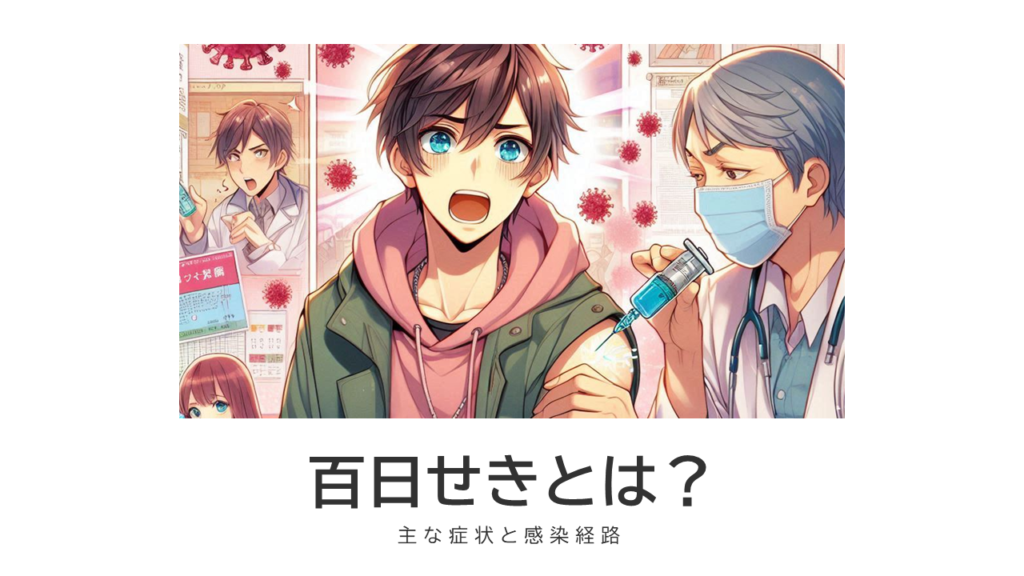
百日せきは、「ボルデテラ・パータシス菌」という細菌によって引き起こされる感染症で、主に飛沫(ひまつ)感染によって人から人へうつります。
🌀百日せきの主な症状(3つの段階)
| 段階 | 症状の特徴 | 期間 |
|---|---|---|
| ①カタル期 | 軽い風邪のような症状(くしゃみ・鼻水) | 約1~2週間 |
| ②けいれん期 | 発作的な激しいせき。息が止まりそうになるほど。 | 約2~4週間 |
| ③回復期 | せきが徐々に減ってくるが、再発もある | 数週間~1か月以上 |
特に、生後6か月未満の赤ちゃんは免疫が不十分で、重症化しやすいとされています。肺炎やけいれん、脳症などを引き起こすケースもあり、命にかかわることもあります。
感染の広がりと地域別の状況
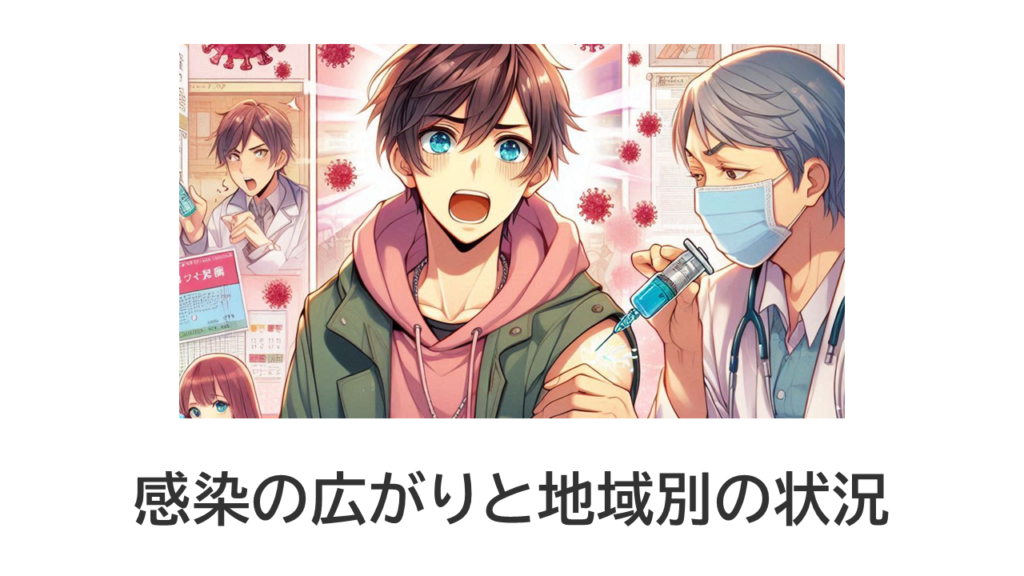
2025年3月の1週間(3月24日~30日)だけでも578人の新規患者が報告され、これは2018年以降で最多の数字となっています。
🗾都道府県別の主な報告数(3月最終週)
| 地域 | 患者数 |
|---|---|
| 新潟県 | 73人 |
| 兵庫県 | 36人 |
| 沖縄県 | 35人 |
| 大阪府 | 耐性菌の報告あり |
さらに、抗菌薬が効きにくい耐性菌が大阪や沖縄で確認されており、全国的な広がりも懸念されています。
ワクチン接種について考える
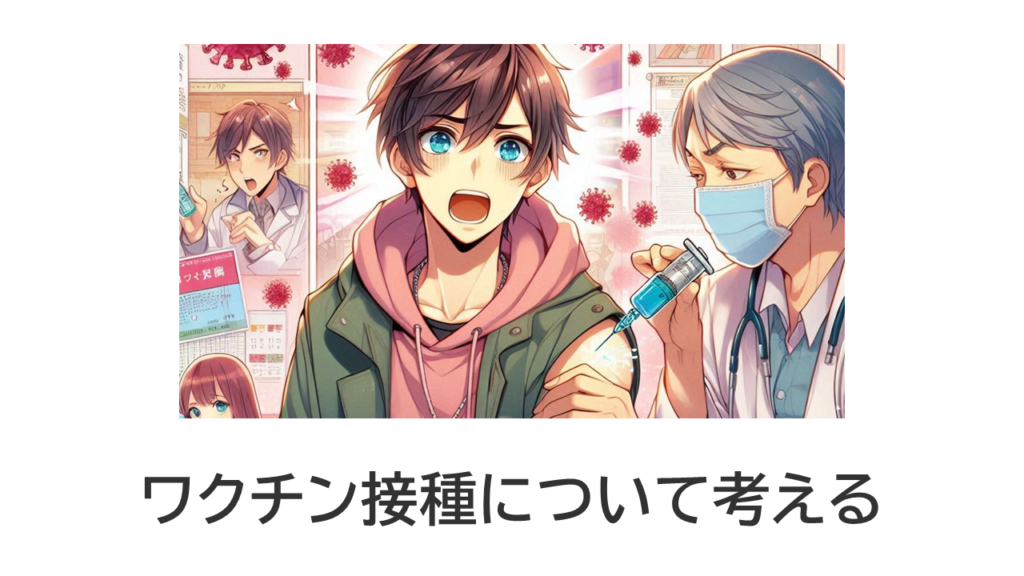
百日せきを含む5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)は、定期接種(公費)の対象で、通常は以下のスケジュールで接種が行われます。
💉標準的な接種スケジュール
| 回数 | 時期 | 接種対象年齢 |
|---|---|---|
| 1回目 | 初回 | 生後2か月 |
| 2回目 | 4週後 | 生後3か月 |
| 3回目 | さらに4週後 | 生後4か月 |
| 追加接種 | 初回終了から6か月以降 | 1歳以降 |
また、日本小児科学会は、小学校入学前や高学年での追加接種(任意)も推奨しています。
📝ワクチンを接種するかどうかの考え方
とはいえ、「流行しているからすぐ打たなきゃ!」と慌てるのではなく、
まずは以下のような情報を確認しながら、冷静に判断することが大切です。
- 家族構成(赤ちゃんや高齢者がいるか)
- ワクチンの副反応・効果に関する信頼できる情報
- 過去の接種歴・免疫の有無
- かかりつけ医の意見
情報収集 → 検討 → 納得したうえで行動、という流れが安心です。
日常の感染予防もとても大切!
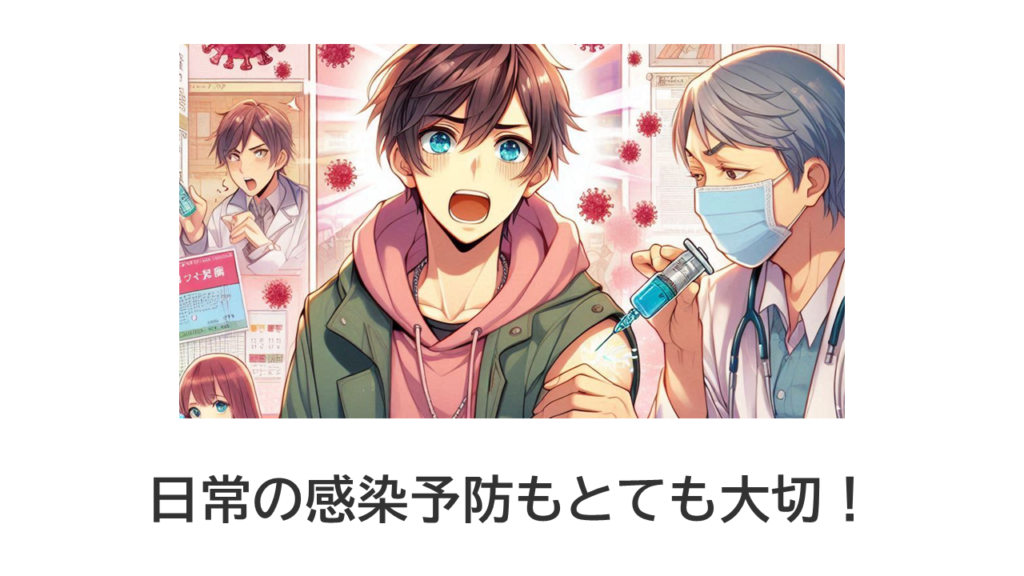
ワクチン接種と同時に意識しておきたいのが、基本的な感染対策の徹底です。
特別なことではなく、毎日のちょっとした習慣がカギになります。
✅家庭でできる予防のポイント
- 帰宅後の手洗い・うがい
- 家族全員の体調チェック
- せきやくしゃみをするときの咳エチケット
(マスク・ハンカチ) - 赤ちゃんを抱っこする前は手洗い・服を清潔に
- 発熱やせきのある人との接触はできるだけ避ける
まとめ
正しく知って、落ち着いて行動を
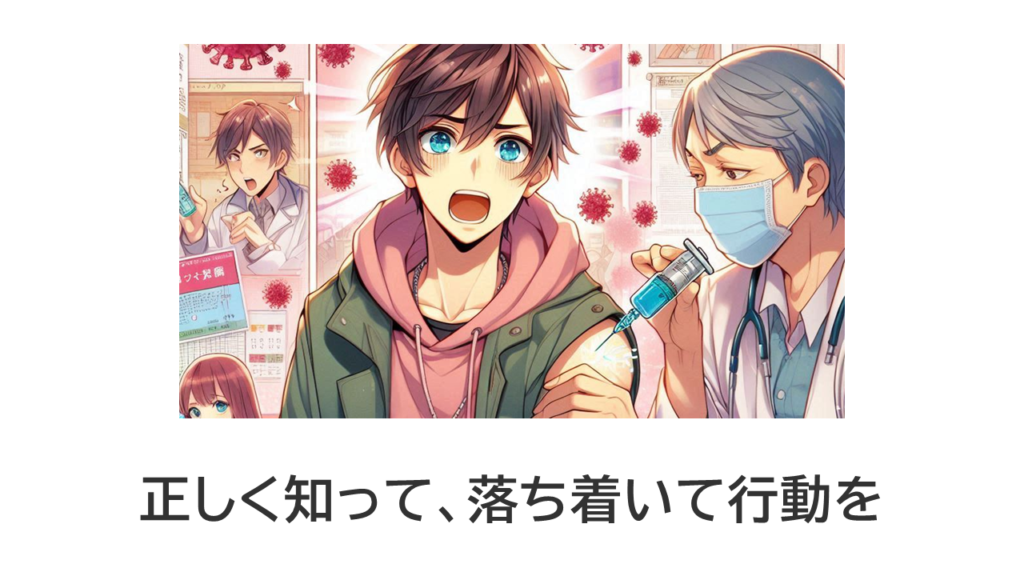
今回の百日せき流行は、コロナ禍で感染が抑えられていた間に、自然免疫を持つ人が減ったことも一因とされています。
ワクチンはその一手段であり、すぐに打つ・打たないではなく、
**「自分や家族にとって、今どうするのがいいか」**を考えるきっかけにしてみてください。
そして日々の小さな予防行動が、家族を守る大きな力になります。